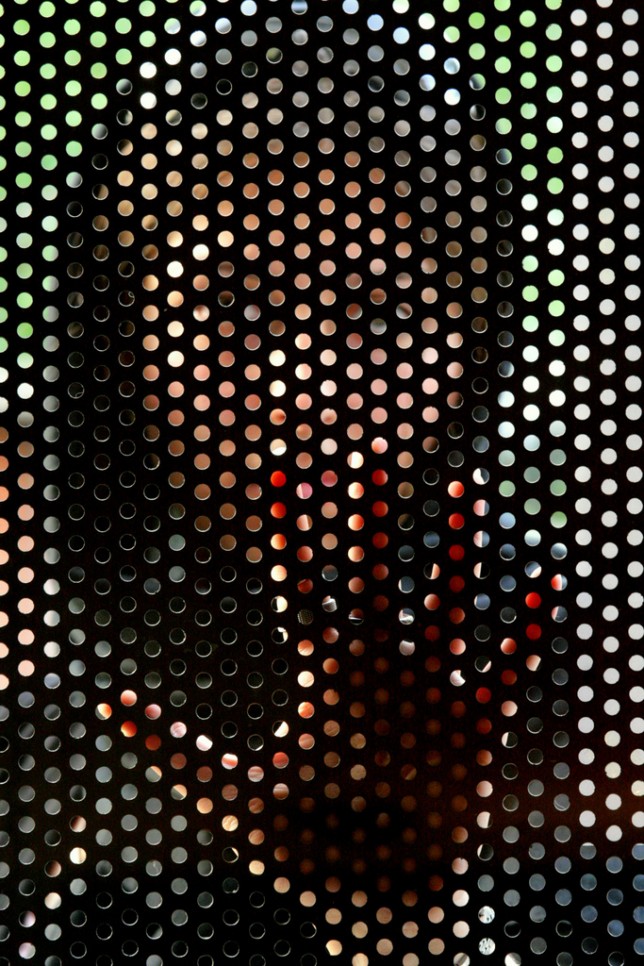68歳の日本人が世界を変えた
もしも、あなたの家の庭から、世界で初めて石油が湧いてきたら?
いつかは尽きるかも知れなくても、いま、間違いなく世界で初めての石油があふれてきたら?
そして、それを世界中の誰もが欲しがっており、あなたの言う値段で買い取ってくれるとしたら?
それなりに高く売ることは当然だといえるでしょう。
値段を下げれば誰もが幸せになると分かっていても、実際にその状況になったら、どこまで値段を下げられるでしょうか?
ましてや、その庭そのものを、誰かにあげることができるでしょうか?
石油やダイヤモンドは、そのようにして価値と歴史が作られてきました。
現代でも、石油やダイヤモンドを独占している国や企業の間で値段が決められ、一部の国の人間だけが、裕福に生きていける仕組みになっています。
しかし、ほんの60年前の1950年代はもっとひどく、世界の石油のほとんどを英国などが独占し、考えられないような高値で販売していました。
持っている者が、持たざる者に決して譲らない。
世界において当然ともいえるこの欲望の構造を変えたのは、なんと何の後ろ盾もないまま、単独でイギリス海軍に立ち向かった日本の民間企業だったのです。
今回は、ベストセラーにもなった『海賊とよばれた男』での国岡鐵造のモデルでもあり、日本の勇敢な経営者として世界的に愛されている出光佐三(いでみつ さぞう)の人生について、わかりやすく解説いたします。
出光という男
出光佐三は、1885年の福岡市に生まれました。
出光は生まれついて病弱であり、特に目が非常に悪く、人生ではっきりとものが見えたことは一度もないと語るほどの弱視でした。
その生涯において独創的な発想を生み出し続けた出光は、「生まれつき目が見えないから、よく考える。だから、私は独創的なんだ」と語っています。本を読むことも出来ないからこそ、とにかく人一倍、懸命に考える努力をしたと伝えられています。
出光はエリート校である神戸大学を卒業し、当時の卒業生は海運会社の社員になることが当たり前でしたが、ひとりだけ石油の個人商店で手伝いとして働き始めます。
このことを、同級生からは「大学のつらよごしめ」とさんざん非難されたそうですが、出光にとっても考えに考えぬいた末の決断でした。
エリートとして歯車の一部になるのではなく、小さな個人商店で、仕事の大部分を扱って勉強したい。最終的に商売人として独立したい。そして、金のことばかりではなく、世のため人のためとなる商売がしたい。
日本が豊かになり、世の中が『金』のために動き出していたこの頃、出光がこのような考えを持つに至ったのは、神戸大学で尊敬していた校長の影響でした。
校長はかたくなに、『金目当ての人間が増えたが、決して金の奴隷になるな』と人の道を説いていたため、このことが出光の心に深く残り続けていたと語っています。
25歳の時、出光は商店の手伝いと、大富豪・日田家の家庭教師を掛け持ちしていましたが、日田はつねづね、出光の人柄に尊敬の念を持っていたそうです。
出光の夢は、『つぶれかけている実家のためにも、早く独立したい。しかしお金がない』というものでした。
悩む出光のために、日田はこんな話を持ちかけます。
「君は独立がしたくても、お金がないと言って苦しんでいるんじゃないかね。
ところで、私が持っている別荘を売却したところ、それが8,000円(現在の8,000万円)にもなった。
このお金は君にあげよう。返す必要もない。利子もいらない。なにに使ったのかの報告もいらないし、好きなように使えばいい。
ただし、必ず独立すること。そして君の弟と仲良く経営してほしい」
出光は考えられないこの大金に驚きますが、今こそ自分の夢を叶える時と決断し、弟とふたりで、石油の小売店である出光商会を立ち上げます。
独立したふたりは、抱えきれないほどの夢と希望を持っていました。
3年で8,000円すべて失う
出光商会を立ち上げた二人に、世間の厳しさが襲い掛かってきました。
当初、日本石油の支店から特約を受け、機械油を扱う商店としてスタートすることができた出光商会ですが、世間では電気モーターが主流であり、利益を上げていくことは困難だったのです。
しかも、金目当てではなく、商人であってもサムライのように仕事をすると決めていた出光は、ワイロを要求してくる人間に対し、「そんなことをしてまで売る気はない」と突っぱねていったため、あっという間に孤立していってしまいます。
わずか3年で、8,000円はつゆのように消えてしまいました。
お金を貸してくれた日田に対して、申し開きもできないほどの惨敗。
出光は商会をたたむことを決意し、日田に謝罪に行くと、日田は出光にこう告げました。
「君は、なぜがんばらない? 3年でダメだったなら5年、5年でダメだったなら10年と、なぜがんばろうとしない? 私の別荘を売って8,000円だったが、私の家は神戸にまだ残っている。これを売れば、運転資金には困らないだろう」
出光はこの日田の申し出に心の底から驚きました。
この恩人に、これ以上家を売却させるようなことをしてはならない。
出光は歯を食いしばって、出光商会を立て直す決心をします。
そして、漁師や業者が、船に高い機械油を使い続けていることに目をつけ、出光の軽油を使えば、もっと安く漁に出ることが出来ると説得します。
これが大当たりして、2,3年後には近隣一帯のすべての漁船や運搬船が、出光の軽油を使いはじめることになりました。
ようやく光が見えた出光は、社会の闇である石油産業の癒着へメスを切り込みます。
世界的に成功するが、敗戦ですべてを失う
当時、満州(中国)の満州国鉄では、外国資本の石油企業が完全な独占状態にあり、日本企業が入り込む余地のない状態でした。
機械油を高い金で満洲国鉄に買い取らせ、ワイロなどが横行し、癒着が蔓延してしまっていたのです。
これを崩すことは並大抵のことではありませんでしたが、出光は真っ向から理を説きます。
「高い油をわざわざ買わずとも、うちの安い機械油を使っても品質に何の問題もない。しかし安い機械油を使えば、国民の負担が減り、必ず国民に喜ばれるのだ」
これらの交渉が、少しずつ満州国鉄の中に味方を生み、ついには外国資本を追い出し、出光が満州国鉄の機械油を扱うこととなります。
その後、中国、朝鮮、台湾へと商売を進めた出光は、社員を1,000人近くも抱え、押しも押されぬ大企業へと成長していきました。
出光は成功したかのように思われましたが、第二次世界大戦での日本の敗北により、すべてを失ってしまったのです。
世界中にあった会社も、資産も、仕事もすべてがなくなり、お金がないのに、1,000人近い社員だけを抱えてしまうことになりました。
なにもない日本の焼け野原で、この時、出光は60歳。
歴史において知られる出光の本当の人生は、ここから始まります。
戦争に負けた程度のことで、大切な社員を放り出せるか
当時の日本は失業者であふれ、戦争に負けために、働くことや仕事をするなどという当たり前のことが、とてつもなく困難な時代になっていました。
日本にいる出光のもとに、海外から何もかもを失った857人の社員たちが戻ってきますが、仕事もお金もありません。
当時の常識として、全員クビにするものだと誰もが考えていました。
しかし出光は、決して一人もクビにすることはないと宣言します。
「この終戦において、考えるべきことは、今までの敵(アメリカら)の長所を見て勉強し、自分たちの短所を反省すること。
そして、堂々と日本人として国を立て直していくこと。
人間は資産であり、海外から戻ってくる857人は会社の財産だ。
出光興産が掲げるのは『人間の尊重』である。
たかが戦争に負けたくらいで慌てふためいて、大切な資産を捨てるようなことがあってはならない」
こうして社員を受け入れるも、実際の出光興産にはまったく仕事がなく、ラジオや醤油・酢の販売、鶏の畜産など、ありとあらゆるものに手を出しますが、どれもまったく上手くいきません。
ついに社員たちに、『待機』を命じるしかない状態になります。
収入がなくとも、出光は自分がコレクションしていた骨董品や絵画を売り払い、社員に給料が支払えるように計らいました。
出光の経営方法は前代未聞であり、社員を決してクビにしないどころか、タイムカードもなし、いつでも好きな時間に働いて帰って良い、定年も設けないという考えられないものでした。
「社員は家族。家族に決まりを作るものがどこにいる」。
この出光の強い信念はきれいごとではなく、実際に行動として示し続けています。
ある社員は、戦争が終わった後やる気が無くなり、田舎にこもり、出光に辞表を出そうとしていました。そこを父親からこう咎められたといいます。
「お前が戦争に行っている6年間、出光さんは毎月ずっと給料を送り続けてくれていた。働いてもいないのに、家族として。ここで会社をやめるなら、6年分タダ働きしてからやめろ!」
そんな出光に、社員たちは自然と信頼で応えるようになっていき、出光興産がふたたび立ち上がる原動力になっていきました。
正しく生きていれば、かつての敵が味方になる
出光がようやく見つけた最初の仕事は、日本を占領しているGHQの石油タンクの底から、ポンプなどではすくいきれない石油を、バケツリレーでさらうというものでした。
巨大なタンクの中に、縄ばしごを使ってふんどし一枚で降り、熱気と悪臭の中、ひたすらバケツリレーするこの仕事は、中毒、窒息、爆発などの危険を常に伴い、体はあっというまに石油でただれていく、とてつもなくおぞましいものでした。
だからこそ誰もやらなかった仕事ですが、出光興産の社員たちは、出光の恩に応えるべく、やっとお金が稼げるようになったこの仕事に取り組みます。
「仕事があるだけ幸せだ」
出光の社員たちはそう言いながら、ひたすらもくもくとこの仕事をやり遂げ、本来では回収できなかったタンクの底油を、1年4ヶ月かけて2万キロリットルも回収することに成功しました。
社員たちはこう考えていました。
石油業界であれほど大企業だった、出光興産のすべてがなくなった。
だから、もはや大企業の誇りは捨て、もう一度石油タンクの中に帰って働こう。
社員は出光への信頼に応えるように懸命に働いたため、その毅然とした態度がGHQの人間たちを感心させました。社員を決してクビにしない家族のような繋がりも、GHQを驚かせたと言われています。
再スタートを切ろうとした矢先に、出光は日本人と戦うことになります。
出光は人間尊重を掲げていたため、石油は自由に業者が競争しながら販売し、価格も下げていくべきだと主張していました。
しかし他の石油業者は、昔と同じように、石油を完全な配給制にして独占的な利益を上げたかったのです。
石油業者たちは一斉に、出光を排除しようとたくらみますが、なんとこの状況から守ってくれたのはGHQでした。GHQは出光の排除を不当とし、出光が石油業に戻れるようにはからってくれたのです。
「正しい道を進んでいれば、いずれ必ず、敵も味方になる」と出光は語っています。
しかし、どれだけ正しい道を歩んでいようとも、敗戦直後の日本の経済は厳しいものでした。
出光興産以外の、日本の石油業者すべてが外国企業の支配下に置かれ、出光はたった一社だけ、日本の企業として孤立することになります。
また、当然ながら海外資本にとって、出光の存在は邪魔でしかありません。出光をつぶすための数々の工作が行われます。
海外諸国が、出光に石油を販売してくれなくなりました。
石油業者でありながら、石油がなく、売ることも買うこともできない状態。出光はもう終わりだろうと誰もが噂していました。
欧米石油資本との戦い
誰も出光に石油を売ってくれない。すべての道は閉ざされた。
それなら、自分で巨大タンカーを作って、石油を売ってくれるところまで買いに行けばいい。
海外には、独立して石油を販売している会社もある。
自分で巨大タンカーを作ってそこまで行けばいい……
しかし、敗戦直後の日本は、物資などなにもないような状態で、政府が決められたわずかな物資を『配給』している状態でした。
特に船などは海運会社が奪い争っており、ただの石油会社に配給するような物資もお金もありません。
出光は政府におもむき、経済安定本部の金融局長に直接訴えます。
「日本に14あった石油業者のうち、13が海外資本の支配下に置かれ、言いなりの値段で石油を販売しています。
高い。とにかく、高い。質の悪いものしか流されてこないのに、それでも高い。
石油はなにをするにも必要な物なのに、今のままでどうやって国を復興させることができるでしょうか?
私は、13の石油業者に対し、ただ1社の日本企業として戦っています。
私がもしも自分の会社のことだけを考えれば、13の企業と同じように海外資本の傘下に入ればいい。そうすれば、1,000人の社員は全員救われます。
しかし、日本国民は、永遠に海外資本の言いなりのまま、高い金額で質の悪い石油を使い続けることになるでしょう。私に、タンカー建造のための費用を頂きたい」
金融局長は、出光の申し出を受け、出光興産にタンカーの建造を許可しました。
こうして作られたタンカー『日章丸』は、なんと規格外れの世界最大級。
当時のタンカーは12,000トンが相場でしたが、『日章丸』は18,500トンという巨大なものだったのです。
出光は世界最大の『日章丸』を使い、海外資本の息がかかっていない、独立系企業との取引に挑みます。アメリカ西海岸を渡り歩き、独立系企業から石油を買取り、日本まで戻ってきたのです。
この行動には、日本のみならず、アメリカ国民をも驚かせました。
敗戦国であり、焼け野原で過ごしていた人間が、まさか世界最大のタンカーを作り出し、海を渡って自分で石油を買い取りに来るなど、夢にも思っていなかったからです。
『日章丸』は、安く買い付けした石油を、『アポロ』という名前で日本国民に販売し始めました。
素晴らしく質が良く、しかも安い『アポロ』は大人気となり、同時に、人々の目を覚まさせたのです。
「こんなに安くていい物でも利益が出るのなら、今までの外国企業に買わされていた石油は一体何だったんだ? あんなに質の悪いものを、敗戦国だからと、言いように高値で売りつけられていたんじゃないか…」
これを見た海外の石油企業たちは、当然『アポロ』の人気を喜ばしく思っていません。
彼らはこう考えました。
出光が、自分のタンカーを作ってまでアメリカの独立起業から買い付けを行うのならば、二度とどこからも仕入れられないように圧力をかければいい。
出光が世界のどの企業からも石油を買えなくすればいい。
こうしてアメリカの独立系企業には、欧米石油資本からとてつもない圧力がかけられ、どこも出光には石油を販売しなくなりました。
せっかく作った巨大タンカーが活躍できなくなり、出光はまたも危機に追いやられたのです。
イランの叫び
当時のイランは、世界でも有数の石油産出国でした。
なにもしなくても、莫大な石油が出てくる現実。
しかし、イランの石油は完全にイギリスが権利を握っており、湧き出る石油利益の90%近くを独占していたのです。
なにもしなくても湧いてくる財産は、がっつりと権利を握り、誰にも渡さない。その国に住んでいる人間にも。
これは、人間の欲望を考えれば当たり前のことですが、イランの人々にとっては、自分の国でこれだけ石油が出ているのに、なぜ、自分たちがこれほど貧しいのかがわかりません。
なんとイランの人々の80%が慢性的な栄養失調に陥っており、食べるものにすら苦労していたのです。
地面の下から石油が出る土地に住んでいるというのに、国民は栄養失調に苦しんでいるという現実。
ついにイランでクーデターが起こり、イギリスの搾取に『ノー』を突き付けました。
「自分の土地から出る石油は、自分たちのもの。自分たちが生きるために使わせてもらう」
このイランの対応は、アメリカに次いで世界2位の軍事力を持つイギリスをとてつもなく怒らせました。
「イランの訴えはまったく何の正当性もない! これより、イランに通じる海域を、イギリス海軍の力で封鎖した。もしもイランと石油の取引に来る船を発見すれば、イギリス海軍の力で撃沈する!」
イギリスが世界に宣言したこの経済制裁は、イランの人々を悩ませました。
しかしそれでも、イランの石油の安さに、多くの海外企業がイランを訪ね、石油契約をしようと持ちかけてきました。
イランは期待しましたが、どこの企業も契約をかわしたっきりで、実際にタンカーを持ってくる企業はひとつもありません。誰もが結局、イギリス海軍の力を恐れていたのです。
莫大な石油利益を、イギリスは絶対に手放さない。イランは誰とも商売などできないと痛感させられていました。
その後、イランに出光の弟である計助が現れ、「石油を買いたい」と言った時、モサデク首相は鼻で笑いました。
「これまで多くの国が、うちの石油を買いたいと話をしにきた。だが、結局、本当にタンカーを出してきた国はひとつもない。お前たちも、そうなんだろう? 結局は、来ないんだろう? イギリス海軍を敵に回して、誰が買い取りに来るものか」
計助は答えました。
「私たちは、そんな不義理はしません」
モサデク首相はこう切り返します。
「ならば、来年の春までに必ずタンカーを持ってこい。必ずだ」
68歳の決断
海外資本からの圧力で、どこからも石油が買えなくなった出光にとって、イランの石油はのどから手が出るほど欲しい存在でした。
しかし、当時のイランから石油を世界で初めて買い取ることは、相当な決断だったといえます。
イギリスが所有権を主張し、イギリス海軍が封鎖しているイラン。
イランから石油を買い取ると、イギリスに対してどうなってしまうのか?
しかし、イギリスがやっていることは、本当に人として正しいことなのか?
石油しか資源がないイランでは飢えに苦しみ、国民の8割が栄養失調になっているのに、自分の足の下にある石油は他国のもの。
それは本当に正しいことなのか?
日本は外国石油資本の犬となり、質の悪い石油を高い値段で買わされて、歯向かう我々には圧力がかかり、石油を仕入れることも出来ない。
敗戦した日本が焼け野原から復興するために、石油が今こそ必要だというのに、なぜ言いなりになって大金を払い続けなければならない?
イランに石油を買い付けに行ったら、殺されてしまうのか?
イギリスは『イランと取引する船は撃沈する』と言っていても、いきなり殺人は犯さないだろう。
しかし、恐らく乗組員は捕まり、船は奪われるだろう。
今の出光興産が『日章丸』を失えば、それこそ石油業界で生きる道はなにもなくなってしまうが…
しかし… それでもイランから石油を買うべきなのだ。
これこそが、本当に人間たるべき道なのだ。
人の幸せを考えれば、飢えに苦しむイランから石油を買い、高値で買わされている日本人のために安く提供することは、人が進むべき大道なのだ。
もしも捕まって『日章丸』を失っても、健全な石油業界作りのために大きな一歩を作れるのなら、船一隻くらい安いものだろう。
68歳になった出光はこの時、何の後ろ盾もなく、ただの日本の民間企業でありながら、イギリス海軍を敵に回す覚悟を決めました。
第三の矢が放たれる
日章丸は、船長と機関長以外、乗組員にすらも目的地を告げず、ひっそりと日本を旅立ちました。
インド洋に向かう途中、「アバダンへ向かう」という船長の宣言とともに、出光からの手紙が読み上げられました。
『出光はこれまで、消費者のためを考えて会社を運営してきた。
消費者のために安く石油を販売するという志は、大儲けしたい多くの国際資本の怒りを買い、数々の嫌がらせをされてきた。
石油をどこからも仕入れられないよう圧力をかけられ、困難な状況を打ち破るために『日章丸』建造という第一の矢を放った。
自分たちで石油を仕入れようと、海外の独立企業との取引という第二の矢を放った。
しかしそこにも圧力がかかり、正に出光は孤立し、たったひとりで戦っている状態だ。
いま、イランのアバダンへ向かって第三の矢が放たれるが、敵は今までで最も強大なイギリス海軍である。
けれどもこれこそが、日本が初めて世界の石油とつながる瞬間なのだ。
誰の言いなりにもならず、自分たちで石油を手に入れ、初めて日本の基礎を作ることができる。今こそが日本の始まりなのだ』……
船員である出光の社員たちは、「アバダンへ向かう」という話に耳を疑い、正気かと考えていましたが、出光の手紙を聞いて、出光のこれまでの行動を思い、国を思い、自分たちのこれまでの生活を思い、決心を固めました。
「自分たちの手で、国の未来が作れるかもしれない…」
船員たちは世の中を変える希望に燃えて、アバダンへと船を進めます。
アバダン到着、イギリスの怒り
アバダンに向かう海路は、整備された海ではなく、あちこちに土砂が流れ込み、いつ座礁してもおかしくない状態でした。
船底が海底でなにかにぶつかれば、その瞬間に船底にヒビが入り、沈没する可能性もあります。
船乗りが最も恐れる事故のひとつであり、スクリューが黄色い泥をかきあげるたび、海底の浅さを実感し、誰もが冷や汗をかいていました。
イギリス海軍に決して見つからないよう、座礁しないよう、静かに静かにアバダンへと船を進めていた日章丸でしたが、ついにマスコミにその存在をキャッチされてしまいます。
UPI通信は次のように報じました。
『アバダンにタンカーで乗り込み、石油取引をしようとしている国があるようだ。
船名や国籍はわからない。しかしこれは…日本のものであるようだ』
日章丸はアバダンに到着しましたが、もうマスコミに知られてしまった以上、逃げることはできません。日本の出光は記者会見を開き、世界に対して、イランと石油取引することを公表します。
「日章丸がイランに到着しました。これからイランと石油の取引を行い、日本に持ち帰ります」
この言葉に世界中が湧き、質問が殺到しました。
これは国際問題になるぞという声、船員たちの命を粗末にしているという声、あらゆる声に出光は毅然として答えていきます。
ある記者からはこう尋ねられました。
「江戸時代に、嵐が起きて江戸にみかんを運ぶことが出来ず、みかんの値段が高騰した時、紀伊国屋という商人だけが嵐の中みかんを運び、莫大な利益を得ましたね。ご感想は?」
出光は激昂して言い返します。
「とんでもない! とんでもない勘違いだ。私が、自分ひとりのちっぽけな利益ごときのために、こんな乗組員の命を粗末にするようなことをするものか。
あなたがたは、私が出光のためにイランとの貿易をしていると思っているのですか?
これは、広く真っ直ぐな道をゆっくりと歩くだけの、人間として自然な歩みなのです。
利益のためでも、名誉のためでもなく、私が日頃から主張している、人間尊重という行動のひとつでしかありません」
この言葉に記者たちは静まり返りました。
自分のことだけを考えれば、国際石油資本が石油を独占している中、自分もその下に入ればいい。すべての日本企業がそうしたように…。
しかし、本当に人々の未来を考えれば、イランの叫びを、奴隷のように過ごす日本人を、本当に見て見ぬふりすべきなのか?
出光は自分の意志を世界に伝えました。しかし、イギリスはこのように声明を出しました。
『日本が行っているイランとの石油取引、壊すためにあらゆる手段を使う必要がある』。
石油を買っても、その後どうしたらいいというのか。
日本に戻れるのか、イギリスとの国際問題はどうするのか。
日章丸は、いまや世界中の人間が注目する船になりました。
イギリスの包囲をかいくぐる
日章丸には、タンカーに載せられる限度いっぱいまでの石油が積み込まれました。
60時間以上かけて積み込まれた石油の重さで、日章丸はずっしりと海の中に沈み込み、なんと船底から海底まで1メートルほどしかないような状態でした。
もしも船底が海底でなにかに接触すれば、沈没する危険性があります。
しかし、安全な海を行くことはもうできないと分かっていました。
船が通るべき安全な海域のすべてをイギリス軍が包囲しており、通過しようとすれば確実に捕まってしまいます。
危険であっても、船の墓場であるスンダ海峡を抜けるしかありません。
スンダ海峡には、戦争中に撃沈された日本の輸送船が大量に沈んでおり、船の上からではほとんど見えませんが、もしもそれらの船に乗り上げてしまったら、その瞬間に船は沈没してしまうでしょう。
目のいい船員が選ばれ、必死に海中にある船の残骸を見極めようとしながら、慎重に船を進めていきます。
戦争で撃沈された日本の輸送船たち。
どうか乗り上げず、自分たちを守ってくれと思いながら進む日章丸でしたが、夜にもなるとなにも見えないので、運を天に任せるしかありません。
ある朝起きると、後方に沈没船の大きなマストが2本あり、知らない間にその間をくぐり抜けていたこともありました。
座礁しなかったのはただの奇跡だとしか思えませんが、沈没した船たちも自分たちを守ってくれたのだろうと、船員たちは勇気を振り絞って船を進めます。
しかし、イギリスの戦略は、海域を封鎖することだけではありませんでした。
あらゆる方法で石油取引を阻止するとは、文字通りすべての手段を使うことであり、日章丸が日本に帰ろうとしている間に、イギリスは日本政府に激しい抗議を行います。
「これは国際問題である。出光興産が日章丸でイランと石油取引していることは、イギリスの法的措置を無視する、許しがたいことだ」
たった8年前、アメリカとイギリス連合軍にぼろぼろにされて敗戦した日本が、イギリス相手に正面から反発する行動を取るとは、誰も思いもよらないことでした。
更にイギリスは、この抗議の後、日本の裁判所に対して『差し押さえ』を要求するだろうことは容易に想像できました。
イランの石油はイギリスのものである。日章丸が持ち帰った石油の一切を、どこにも売ることは許さない。すべてイギリスが差し押さえる…。
出光は、イギリス海軍との海の戦いと同時に、裁判による陸の戦いにも勝たなければならなくなったのです。
イギリスとの裁判
出光は必死にこの状況を打開するために頭を張り巡らせました。
――もしも、日章丸が日本に着いた瞬間に船ごと石油を差し押さえされたら、もうどうしようもない。そこから解決できる方法はないだろう。
最大の抜け道は、裁判所が日曜日休みであること。
土曜日の昼頃に日章丸を到着させ、同時に、裁判所には「いきなり差し押さえず、こちらの言い分も聞いてくれ」と伝える。
これにより、イギリスと我々との口頭弁論が始まるが、土曜日中には決着がつかない。
日曜までもつれこんでも、日曜日に法廷は休みである。
まず、積み荷を下ろすことが出来、完全な差し押さえを受けてしまうことはないはずだ――
これと同時に出光は記者会見を行い、イランとの石油取引は公正であり、国際的にもなんらルールに反する行動ではないと主張しました。
裁判は9日から始まることになり、いよいよイギリスとの裁判が始まります。
この敗戦直後の日本で、ただの民間企業が、堂々とイギリス相手に裁判で戦うなど、考えられないような話でした。
イギリスは裁判で、出光に強く切り込んできます。
「イランは、自分の国の石油を自分のものだと言っているが、これは彼らが勝手に言っていることであり、我々イギリスはまったく認めていない。
つまり、今も、石油は我々のものなのだ。
裁判所には、出光が今回の石油を一切どこにも販売しないよう、仮処分命令を出してもらいたい。
また、日章丸は続々と積み荷の石油を陸にあげている。これをどう横流しするか分かったものではない。即刻、船ごと差し押さえしてもらいたい」
出光側の弁護士はこう答えました。
「出光は、何も話が進まないまま、石油を売り払うようなことはしない。船から陸にあげれば、そのままにしておくことを約束する」
イギリス側は鼻で笑います。
「そのようなことが、信用できると思っているのかね。出光の社長が何をするか、わかったものではない」
裁判長はこう告げました。
「出光の社長がちょうどここにいる。彼から証言を取ってみてはどうでしょうか」
出光は証言席に立ち、イギリスが激しくにらみをきかせる中、毅然として主張します。
「この問題は今、国際問題になっています。
しかし私は、日本国民として、自分の心にも自分の行動にも、一点も恥じることなく、裁判を最後まで行うことを誓います」
このあまりにも堂々とした主張に、法廷の中には感嘆の声があふれました。
敗戦国である日本で、強大なイギリスとの裁判が始まります。
しかし、『正道を行くのみ』と常に主張している出光には、いつしかたくさんの味方がつくようになっていました。
搾取から目を覚まされた
出光の多くの行動は、新聞を通じて、無関係であったようでいて、実は多くの日本人の心を震わせていました。
誰もが、敗戦後、焼け野原になった日本で、いつしか心も卑屈になっていたのです。
言いなりになるまま、高い金で石油を買い、生活も安定せず、敗戦国の人間という大きな負の言葉が頭の上にのしかかっていました。
アメリカやイギリスに逆らうなど、もってのほか。
しかし出光は、なぜ、こんなことができるのか??
なぜ、イギリスに対して噛み付いていけるのか?
イランにやっていることが間違っていると分かっていても、石油を独占することがずるいと思っていても、誰もが「そういうものだ」と息を殺していた時に、なぜこんなに堂々と噛み付いていく?
自分にはなにもできないが、せめて、あの人を応援したい。
日本中に出光を応援する声が響き、世論は、『出光を処分したら許さない』という方向に流れて行きました。
出光が敗戦後、社員に対して行った宣言は、「愚痴をやめろ。もう後ろを振り返るな。ただ、自分たちを反省し、ただ、アメリカやイギリスの長所には学ぶこと。そして、堂々と日本を立て直していくのだ」ということでした。
本当に出光がこれを行おうとしていることを知り、人々はそこに希望を見つけたのです。
イギリスは、戦争で勝ったというおごりがあり、また、戦勝国は敗戦国になんでも言えるとも考えていました。
しょせん、日本は我々の属国。こちらの言い分がどれだけおかしくとも、『負け』だけは絶対にない―――――
しかし、裁判の結果はイギリスの予想を大きく裏切るようなものでした。
『イギリスの言い分を却下し、裁判にかかった費用もイギリスの負担とする』。
日本中が喜びの声に震える中、イギリスは怒り、控訴も行いましたが、最終的には諦めざるを得ませんでした。
出光の思いと行動は、日本国民だけでなく、裁判所をも動かし、搾取と独占が当たり前であった石油のルールを変えたのです。
イランは飢えから救われ、日本人は粗悪品を高値で売りつけられることもなく、石油製品は一気に値下がりし、日本の高度成長期を支えました。
まさに、68歳の老人の決断が、世界を変えた瞬間でした。
「日本人に、感謝の気持ちを伝えて欲しい」
裁判を終え、日章丸が2回目の石油取引のためにアバダンへ向かうと、そこにはイラン人たちの歓迎の嵐がありました。
日章丸が到着することを待ちきれない少年たちが丸太船で近づき、大歓喜の声を上げ、人々は港でシーツを振って日章丸の到着を歓迎し、空には飛行機が舞い上がって、空中から色とりどりの花を振らせ続けます。
「ジャパン!! ジャパン!!」と叫ぶイランの人々の歓喜の声は終わることなく、乗組員たちの胸を震わせました。
モサデク首相は日章丸の乗組員を呼び寄せ、握手をしながら深く深くこう言いました。
「あなた方日本人の勇気と偉大さを、イラン人は永遠におぼえているだろう。
今は焼け野原の日本でも、必ず、あなた方はまた立ち上がると信じている。
お互いに東洋人として、ずっと協力しあっていこう。
あなた方は我々の救世主だ。どうかこの思いを、すべての日本人に伝えて欲しい」
イランには、どの国も自由に石油を買い付けにこれるようになりましたが、最初の日本との石油取引だけは無料とし、その後も日本だけは、半年間の取引のすべてを半額としました。
正道を行くという出光の思いは、イランの人々にも間違いなく伝わっていたのです。
「あなたの努力ですよ」
その後、出光興産はイランからの石油を販売することで石油業界に返り咲き、消費者優先の事業を行うことで、日本有数の石油企業としてその地位を確立していきました。
イランから石油を買い取った『日章丸事件』から3年後である1956年には、徳山湾に日本最大の製油工場を建設し、正に日本を代表する石油企業になっていったのです。
この工場の建設が完成した時、出光には、どうしても呼ばなければならない人間のことが心の中にありました。
それは、自分がまだ個人商店の使いっ走りで、家庭教師をしながら生計を立てていた時、そんな自分を高く買ってくれ、何の約束もなく8,000円(現在の8,000万円)を貸してくれた大富豪・日田のことです。
出光は82歳になっていた日田を、日本最大の製油工場の竣工式に呼び寄せて、「すべては、あなたの御恩のおかげです」と深く深く頭を下げました。
日田は優しく、「あなたの努力ですよ」と言いながら手を差し出してきたため、もう出光はそれ以上言葉にならず、深く手を握り返し、そのまま、しばらく離すことができなかったといいます。
出光はずっと日田に対する恩を忘れておらず、日田が年老いてからは、日田のことを思いやれる社員を毎晩日田の家に向かわせ、晩酌の語り相手をさせたり、自分の別荘を提供したりしてきていましたが、日本最大の製油工場を立てた今、ようやく日田との約束を果たせた思いでした。
日田が亡くなった時、出光はこれを『社葬』として扱い、自分自身が出席して、会社ぐるみでその死を弔います。
その後、93歳まで生きた出光は、多くの人々に影響を与えたその人生を終えるのですが、出光と40年以上も苦楽をともにした側近の石田は、出光についてこう語りました。
「40年以上ものつきあいで、生涯のうちでただの一度も、彼は私に『金を儲けろ』とは言わなかった」
若き日に、人間の尊重などの美しい思いを掲げることは誰にでもありますが、最後までその思いを貫き続けた出光は、多くの人間に慕われながら、独占状態だった石油業界を変えた人間として、その行動力に敬意を表されています。